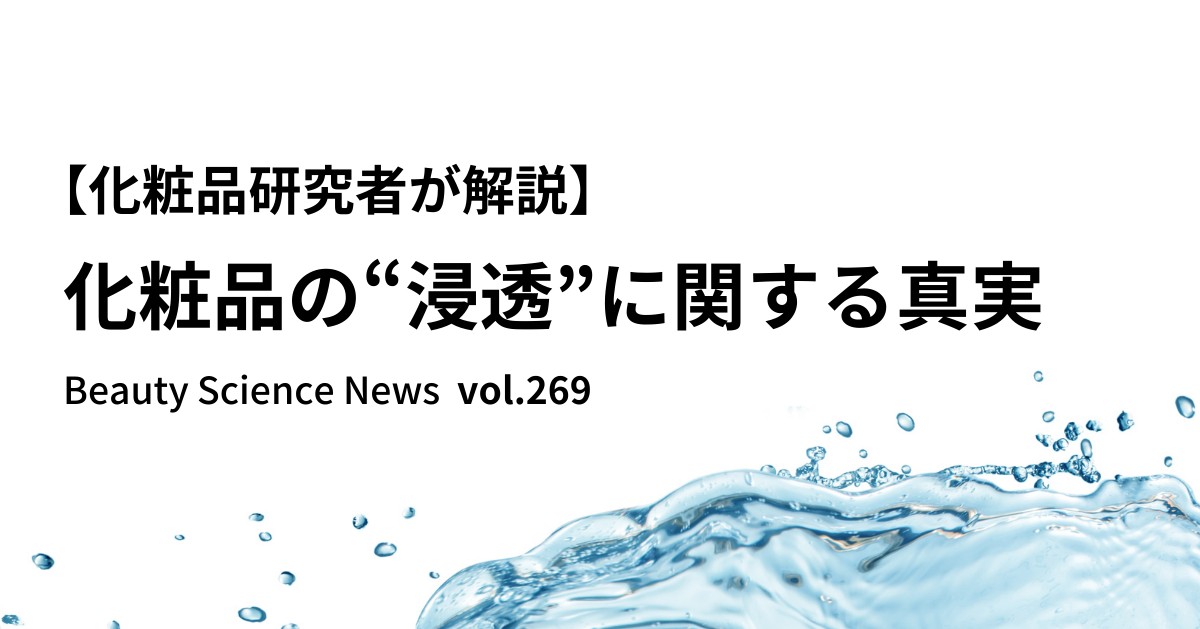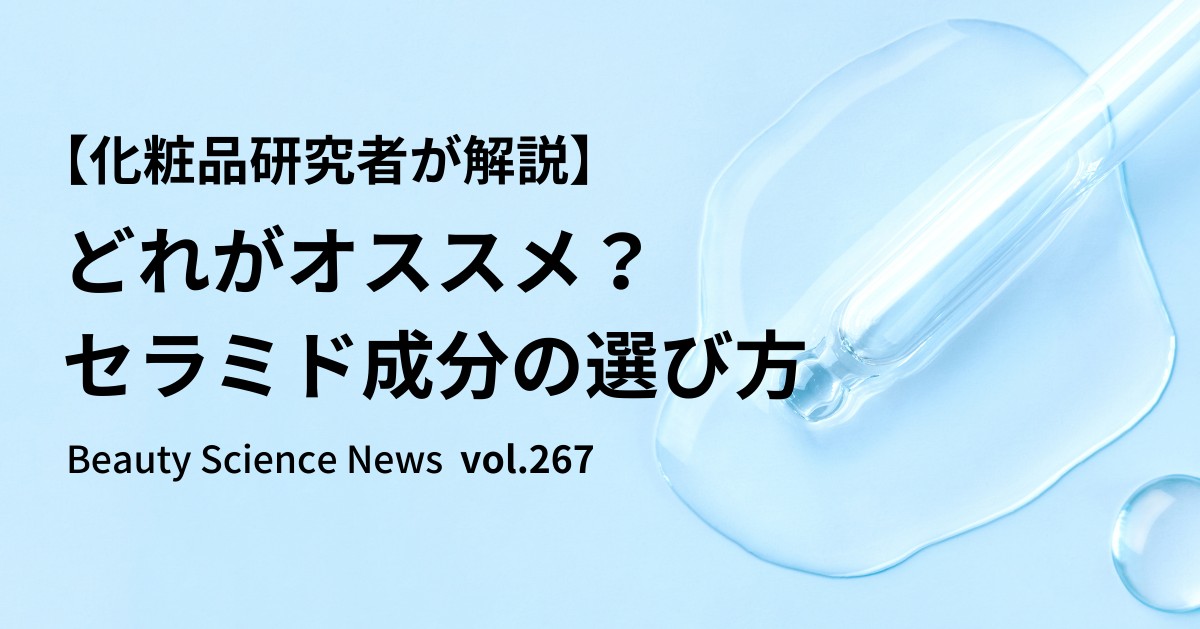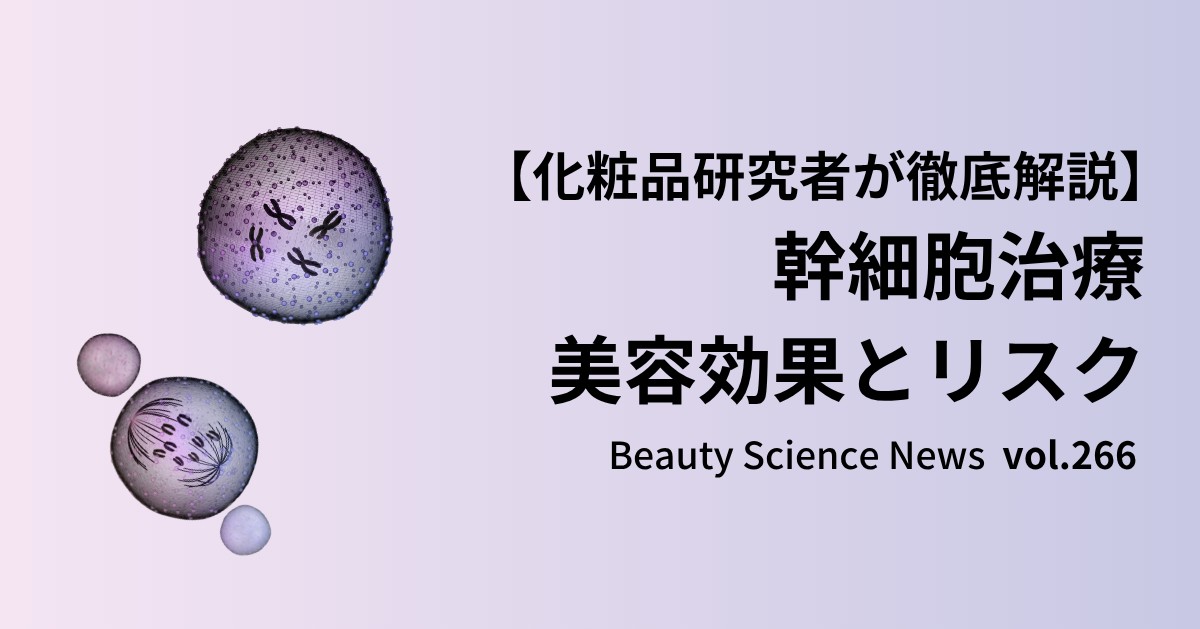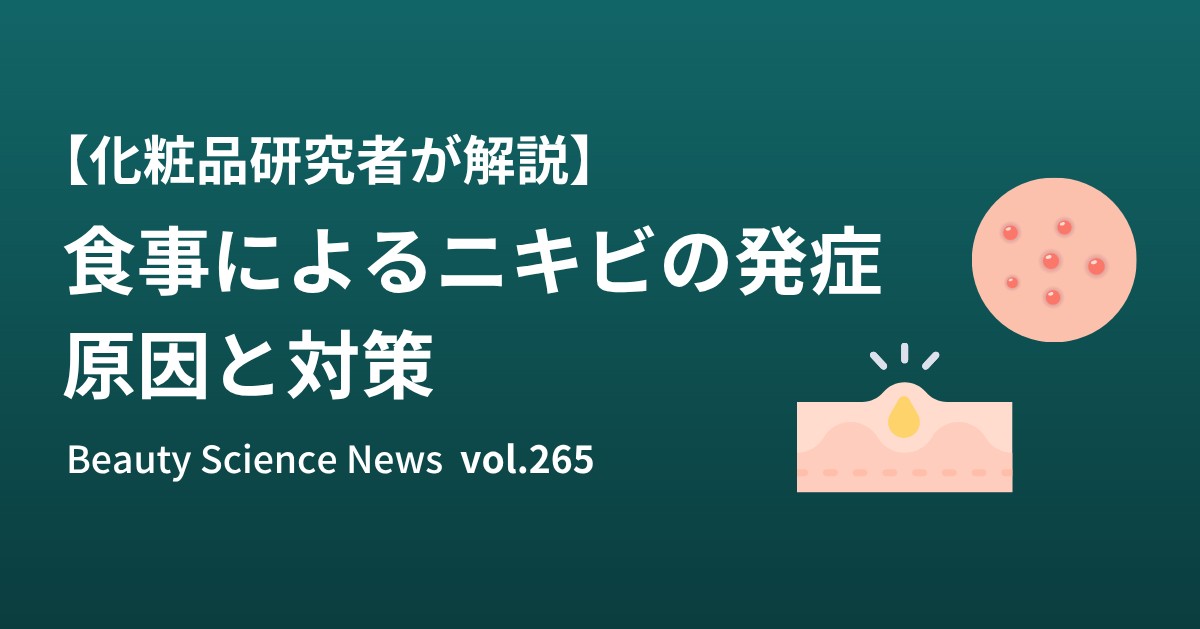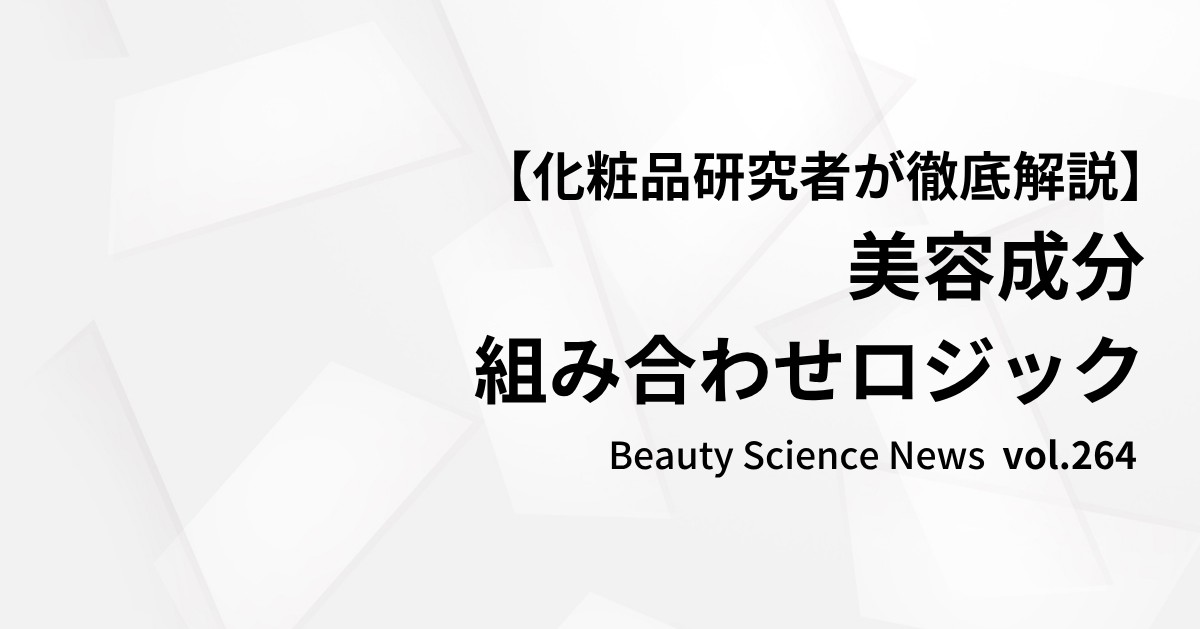ワセリンとグリセリン、どっちがオススメ?化粧品研究者が徹底解説!

保湿は美しい肌を実現するために必須の要素であることは言うまでもありません。多くの皮膚科医・化粧品研究者が保湿の重要性についてSNSなどで発信していますよね。
そして肌を保湿するために利用されるのが保湿剤です。皆さんもご存知のように保湿剤には様々な種類がありますが、その中でも最も多く利用されているのがワセリンとグリセリンでしょう。
この2つの保湿剤は多くのスキンケア製品に配合されており、我々化粧品研究者にとっても馴染みの深い成分です。皆さんがお使いの製品にも、これらの成分が配合されているものは多いのではないでしょうか。
本記事ではこのような保湿剤の選び方やオススメの使用方法について、それぞれの成分の保湿メカニズムの観点から分かりやすく解説したいと思います。
-
肌の保湿はなぜ必要なのか?
-
ワセリンとグリセリンの保湿メカニズムの違い
-
肌タイプ別のオススメ保湿剤
上記のポイントを中心に、現役の化粧品研究者が科学的根拠に基づいて徹底解説します。
また本ニュースレターでは無料会員・有料会員のメンバー登録を募集しています。毎週配信されるニュースレターを見逃さないようにするためにも、ぜひメンバーシップに登録頂けると嬉しく思います。
上記の登録ボタンからメールアドレスで簡単に登録できますので、ぜひこの機会にご検討ください。それでは早速解説を始めていきましょう。
「肌を保湿すること」の重要性
美しい肌を実現するために保湿が重要であるというのは多くの方がご存知の美容知識だと思います。
一方で、そもそもなぜ保湿が美容に重要なのかについて皆さんは科学的に説明できるでしょうか?保湿が重要なのは美容の常識ではありますが、まずはその科学的根拠について詳しく解説していきたいと思います。