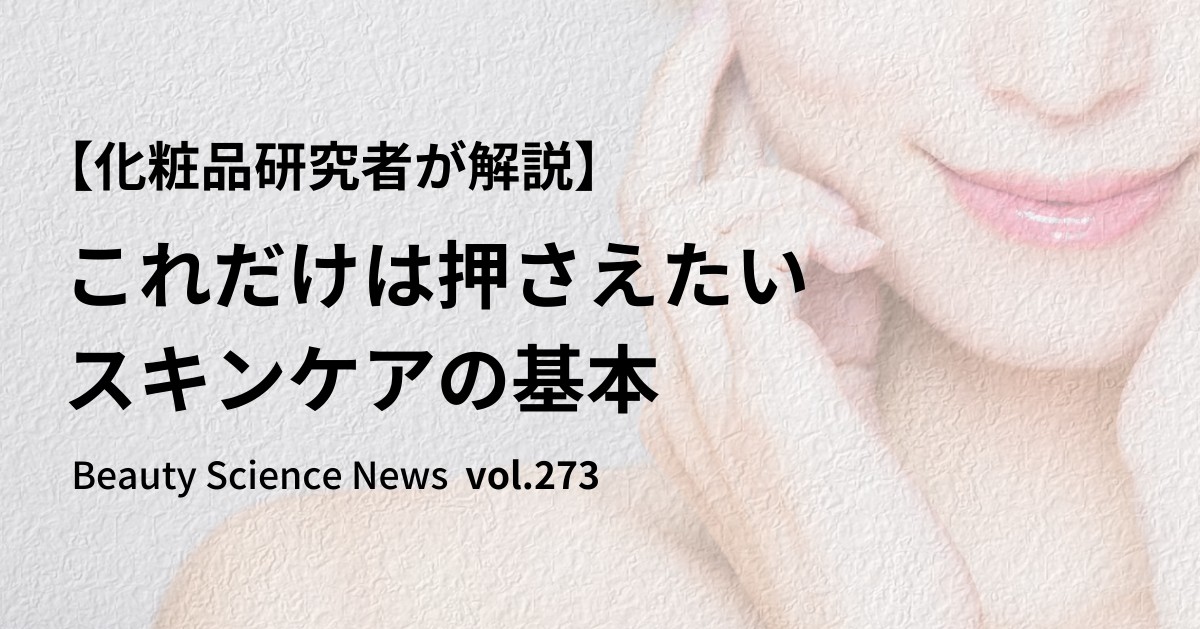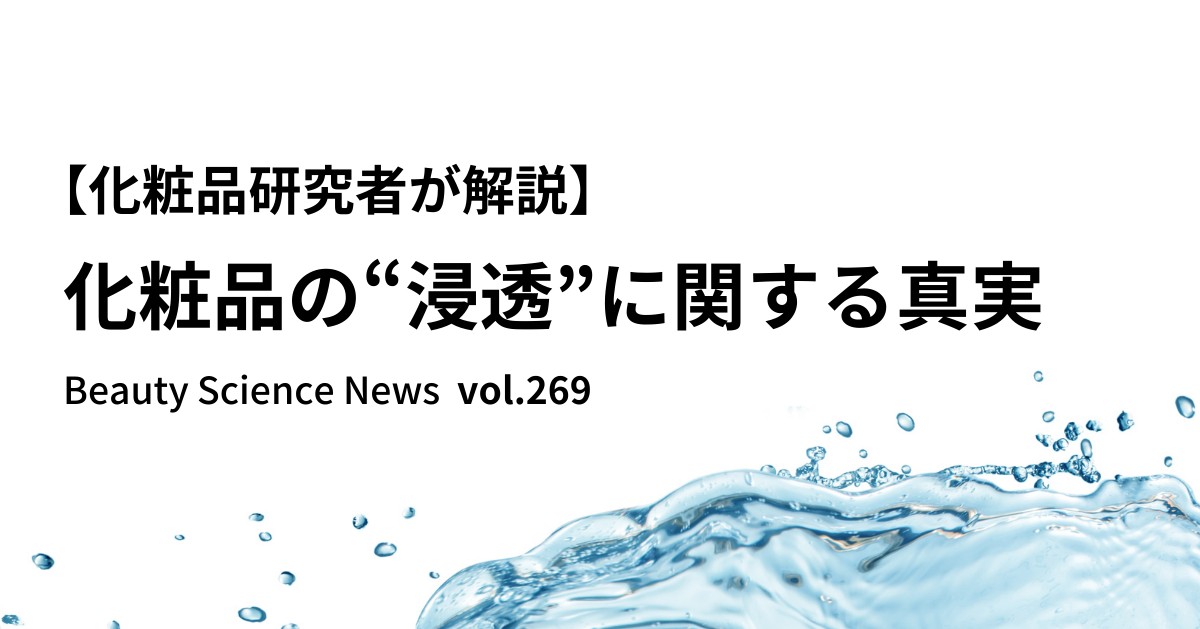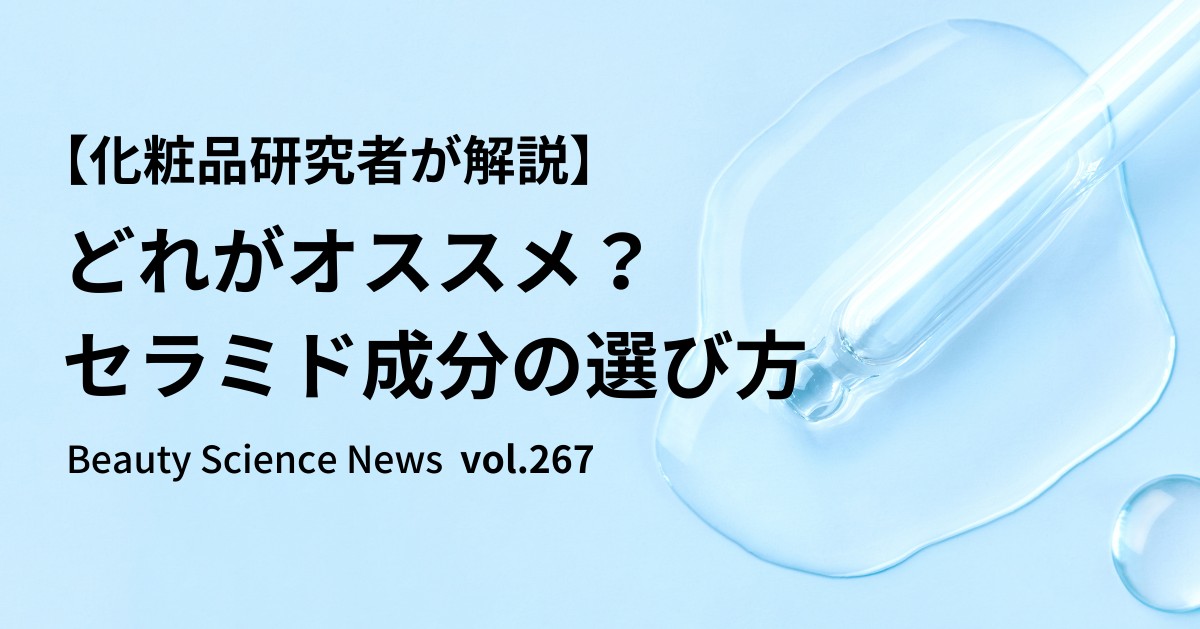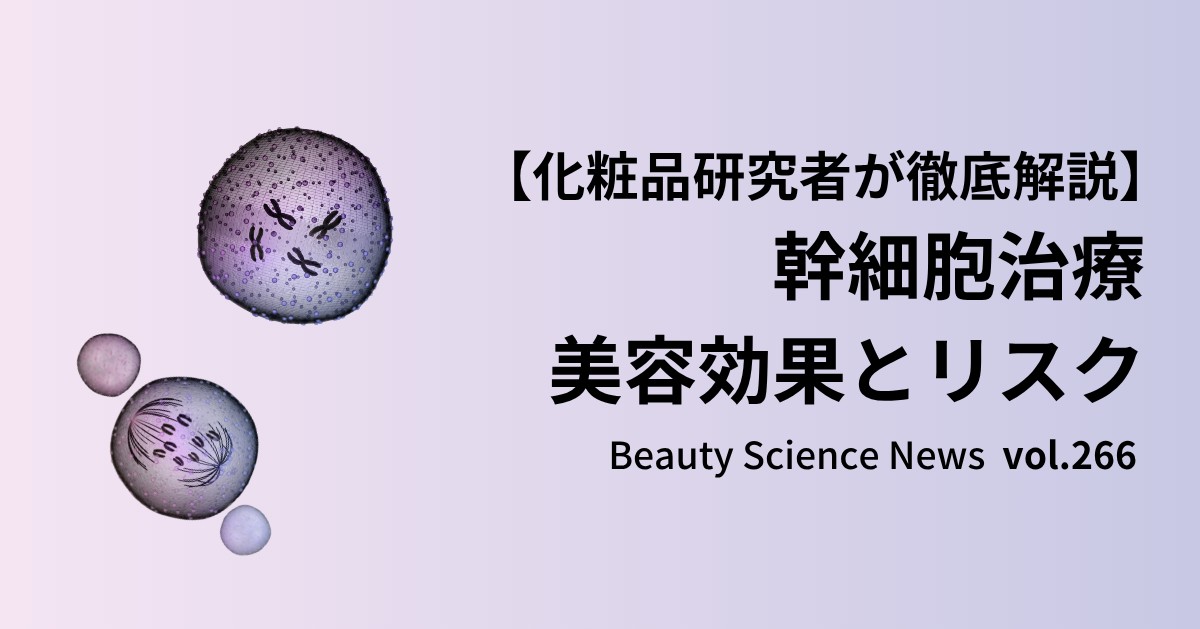ストレスは肌に悪いって本当?最新研究を徹底解説!

現代人にとってストレスは切っても切り離せない関係にあります。適度なストレスは身体に程よい緊張感を与えますが、逆に過度なストレスは精神疾患を引き起こすなど様々な悪影響をもたらします。
そして近年ではストレスが肌の状態にも悪影響を与えるという噂をよく目にするようになりました。SNSではストレスはお肌の大敵だから溜め込まないように!という投稿をよく見ますが、果たして本当にストレスは肌に悪影響を与えているのでしょうか?
本記事では現役の化粧品研究者が、ストレスが肌に与える影響を科学的根拠に基づいて徹底解説します。
-
ストレスが肌に影響を与えるメカニズムとは?
-
ストレスと肌状態に関する研究報告
-
科学的根拠に基づくストレス解消方法
主に上記のポイントについて論文や研究情報を分かりやすく解説します。
目まぐるしい社会の変化の中でストレスを感じているという方も非常に多いと思います。ぜひ本記事を参考にしてストレスと肌の関係性について学び、身も心も健康的な身体を導いて下さい。
また本ニュースレターでは無料会員を随時募集しております。今後ニュースレターの配信情報を見逃さないようにするためにも、ぜひこの機会にご登録頂ければ幸いです。
以下のボタンからメールアドレスで簡単に登録できます。
それでは早速解説を始めていきましょう。
結論:ストレスは肌に悪影響を与える
さて早速ですが今回は初めに結論から示したいと思います。結論としては、近年の研究動向を鑑みるとストレスが肌に悪影響を与えることはほぼ間違いないと言えると思います。
もちろん影響の大小は少なからずありますが、「なんとなく肌の調子が悪い」程度の影響であればストレスが原因になっている可能性は十分にあると私は考えています。
なぜストレスが肌に悪影響を与えるのか?については現在でも正確なことは明らかになっていませんが、考えられる一つの原因としてストレスにより放出されるホルモンの影響が報告されています。
例えばポーラは、ストレス負荷によって血中で増加するホルモンであるコルチゾールが皮膚細胞に悪影響を及ぼすことを報告しています。培養表皮細胞にコルチゾールを添加すると、肌のバリア機能維持に極めて重要なフィラグリンと呼ばれるタンパク質の発現量が低下することが確認されています。

引用:ポーラ化成工業 ニュースリリース
特に興味深いのは、50代に由来する皮膚細胞よりも30代の皮膚細胞の方がコルチゾールの影響が大きかったという点です。細胞系の検討であるためあくまで推定になりますが、この結果は若い女性の方がストレスによる肌不調の影響を受けやすいということを示唆しています。

引用:ポーラ化成工業 ニュースリリース
さらにノエビアグループの報告によれば、コルチゾールはオキシトシンと呼ばれるホルモンの受容体を真皮線維芽細胞において減少させる働きがあることが示されています(参考)。
オキシトシンは別名「幸せホルモン」とも呼ばれる有名なホルモンであり、幸福感を感じた際に分泌されることが知られています。近年ではオキシトシンが美しい肌状態に関連する可能性が報告されており(参考)、これらの研究結果からもストレスと肌状態の深い関連性が見て取れます。

引用:花王 唾液中のオキシトシン量と肌の質感との関連性を確認
まだまだ不明な点も多いのは事実ですが、ストレスがホルモンの分泌を介して肌に悪影響を与えている可能性は高く、多くの化粧品メーカーで研究が進んでいます。
ではストレス負荷やストレスの軽減によって具体的にどのような肌の変化がもたらされるのについて、更に研究結果を詳しく見ていきましょう。
精神的ストレスと肌状態に関する研究結果
それでは実際に精神的ストレスと肌状態に関する研究結果を解説していきます。ストレスやストレスの軽減が肌にどのような影響を与えるかについて、具体的な研究例を通して理解を深めて頂ければと思います。
The Effects of Relaxation Before or After Skin Damage on Skin Barrier Recovery
2015年にニュージーランドの研究チームから報告されたこちらの論文では、皮膚損傷からの回復過程におけるリラクゼーションの効果が検証されています。
121名の健康な成人を以下の3つの群に分け、テープストリッピングによる皮膚ダメージを加えた際の回復過程を、皮膚バリア機能を表す経皮水分蒸散量(TEWL)の変化によって観察しています。
-
リラクゼーション後にテープストリッピング
-
テープストリッピング後にリラクゼーション
-
テープストリッピングのみ(対照)
このような実験を行った結果、対照群と比較してリラクゼーション介入を行うことで、双方(テープストリッピングの前後)とも皮膚バリア機能の回復が高まることが確認されました。
リラクゼーション介入を行うことでテープストリッピングによる痛みの低減効果も確認されており、リラックス効果が肌に良い影響をもたらす可能性が示唆されます。
ストレスと皮膚―過密ストレスモデルによる皮膚生理学的変化―
少し古いですが1997年に報告されたこちらの論文では、ストレスが肌に及ぼす影響を皮膚色測定や皮膚組織学的解析の観点から検証しています。
主要な結果としては、ストレス負荷を与えることで皮膚色に以下のような変化が確認されました。
-
L*値(明度)・b*値(黄色み)の上昇
-
a*値(赤み)・C*値(彩度)の低下
一般にL値とC値は高い方が好ましく、a値とb値は低い方が良い肌色を示す傾向があります。この結果から一概に肌色が悪くなったとは言えませんが、ストレスによって肌の色味が変化することは事実と言えそうです。
さらに組織学的手法を用いて表皮DOPA染色を行った結果、メラノサイトにおけるメラノジェネシス(メラニン合成)が増加している様子が確認されました。すなわち、ストレスが表皮のメラニン合成を高める可能性があるということです。
これらの結果から、ストレスが皮膚そのものに対しても様々な影響を及ぼしていることが明らかとなりました。特に皮膚色の変化やメラニン合成活性が高まりが確認されたことから、ストレスがシミやくすみの原因となる可能性が十分に考えられます。
ストレスマーカーと皮膚状態の関連性解析
ストレスマーカーと皮膚状態の関連性を解析した研究についても2つご紹介します。
まずこちらの論文では、ヒトがストレス要因にさらされた際に分泌されるバイオピリンに着目し、皮膚との関連性が調べられています。
高齢女性44名を被験者とし、尿中バイオピリンと皮膚角質層水分量(前腕内側部と後頸部)との関係を調査した結果、いずれの部位でも負の相関性、すなわちバイオピリンが多いほど水分量が低くなることが確認されました。
また皮膚水分量の多い群と少ない群を比較した結果、尿中バイオピリン濃度に有意な差が認められました。これらの結果は、ストレスが皮膚の水分量を低下させる可能性を示唆しています。
またサティス製薬によるこちらのリリースでは、冒頭に解説したストレスホルモンのコルチゾールと肌状態の関係性がヒトで検証されています。10から70代の女性の約300名を被験者とし、精神的ストレスの指標である唾液中のコルチゾール量と肌の粘弾性との関係を解析しました。
その結果、唾液中のコルチゾール濃度が高い被験者群は肌の粘弾性が低く、コルチゾール濃度が低い被験者群は粘弾性が高いことが分かりました。粘弾性は肌のハリや弾力を反映する指標であるため、この結果はストレスが大きくなることで肌のハリや弾力が低下する可能性を示唆する結果と言えます。
いずれの研究もメカニズムに踏み込んだ検証は出来ていませんが、相関解析レベルでストレスと肌との関係性が見えつつあります。
ストレスを解消する方法
これまでに解説したように、ストレスは肌に一定の悪影響を与えている可能性が多くの研究で報告されています。もちろんその影響は紫外線や乾燥に比べれば小さいと考えられますが、少なからず肌に影響を与えている可能性はあると言って間違いないでしょう。
やはりストレスを溜め込まないようにすることは、美容にとっても一定程度の重要性があると思います。ではどのようにすればストレスを解消できるのでしょうか?最後に科学的根拠に基づくストレスの解消方法についてご紹介したいと思います。
今回は科学的根拠が多数報告されているストレス解消法として、マインドフルネス瞑想をご紹介させて頂きます。以下にソースとなる論文を記載致します。
マインドフルネスは近年流行しつつある思想であり、既に実践しているという方も多いかもしれません。元々は仏教の思想に由来する考え方ですが、近年では臨床研究レベルでもその有効性が確認されており論文も多数報告されています。
Wikipediaによると、マインドフルネスとは「現在において起こっている経験に注意を向ける心理的な過程である」と定義されています。ごく簡単に言うと、目の前の状況に意識を集めるという思想です。
この思想を瞑想に活用したのがマインドフルネス瞑想で、多数の論文によりストレス低減効果が科学的に実証されています。具体的な方法としては、今現在起こっている音・感覚・思考・感情・動作などに注意を向けつつ瞑想を行うことが挙げられます。
例えば呼吸の音にのみ意識を向けて5~10分の瞑想を行うだけでもマインドフルネス瞑想に当たります。詳しい瞑想方法についてはネット等でも詳しく解説されていますので、興味のある方はご覧下さい。
マインドフルネス瞑想に限らず、何かに没頭する作業はストレスを低減する作用があることが知られています。例えばアート制作やスポーツなど、ストレスの要因となる意識を排除し目の前の出来事に没頭できるような環境が、ストレスの低減に効果的です。没頭できる何らかの趣味に取り組むことも良いでしょう。
コロナウイルスの拡大に伴いストレスを感じる環境も大きく変化しています。自宅で簡単に出来る瞑想などを一日10分程度でも実践することで、ストレス低減から美しい肌を導くことが出来るかもしれません。ぜひ本記事を参考にして、皆さんも実践してみて下さい。
まとめと編集後記
以上、今回はストレスと肌の関係性について科学的根拠を元に解説しました。やはりストレスが溜まっていると肌の調子が何となく悪いという方は私の実感としても多いように思います。
もちろん美容の基本は紫外線対策と保湿・マイルド洗顔ですので、これらに勝るスキンケアはありませんが、ストレスケアによる美容のアプローチも今後ますます重要になってくると思います。その証拠に化粧品メーカーによるストレス研究も近年多数報告されていますね。
ストレスは美容に限らず様々な精神疾患と関連しています。身も心も健康的にあることが、美容にとっても極めて重要です。ぜひ本記事を参考に、ストレスの低減についても今後意識してみて下さい。
またBeauty Science Newsでは、以下のメリットがある有料プランもご紹介しています。
-
科学的根拠に基づいた美容知識が毎週届く
-
自分に合う化粧品を成分レベルで選べるようになる
-
ネットやSNSに存在する怪しい美容情報に騙されなくなる
-
70本以上の有料記事を好きな時に読むことが出来る
科学的根拠に基づいた美容情報を継続して受取りたい方は、ぜひ有料会員登録もご検討ください。有料会員には以下のページからメールアドレスで「ログイン」後、クレジットカードで登録することが出来ます。
有料会員にご登録頂ければ、月4~5回の美容科学記事配信(無料会員は月1回配信)と共に、過去の有料記事もweb上で全て読むことが出来ますので、この機会にぜひご利用頂ければと思います。
また有料購読の解除はいつでも可能ですのでご安心ください。もちろん無料の購読登録も大歓迎ですので、まだ登録をされていない方はこの機会にぜひご登録ください。
今週も読んで頂きありがとうございました。それではまた来週、お会いしましょう!
・最先端の美容情報をお届け
・過去の記事も読み放題
・毎週届き、いつでも配信停止可
・読みやすいレターデザイン
すでに登録済みの方は こちら